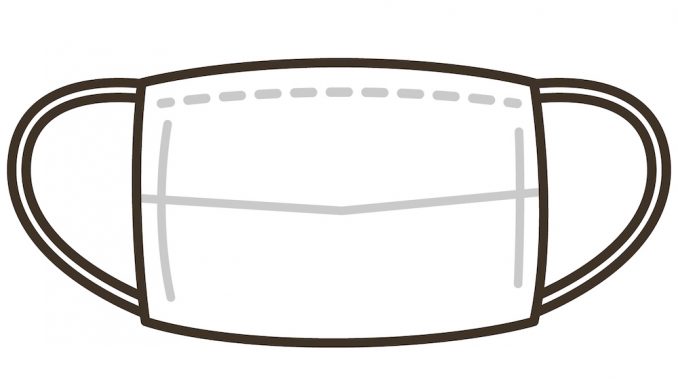
最終更新日 2025年5月19日
マスクとは人の顔を覆うものという意味があり、面やプロレスラーが目と口だけ出して被るようなものもありますが、ここでは鼻と口を覆うものについてマスクに詳しい神澤光朗先生に聞いてみました。
マスクの構造と種類
マスクには、医療用と家庭用、防塵用など用途によって構造も変わってきます。
種類としてはN95とサージカルがあり、N95というのは、「NIOSH」といわれる米国労働安全衛生研究所が定めた規格のもので、空気中にある脂分以外の固体と液体の噴霧状になったものを95%除去できるという効果をもち、N95の規格に合ったと認定されるものです。
N95は顔面に密着するような構造で、外気中の微生物や感染源から人を守ることを目的として作られていて、主に工事現場などの防塵用として使われています。
しかしN95は目が細かすぎて、長時間の着用で息苦しくなるというデメリットも有しています。
外科用のサージカルは、感染源や微生物の侵入を防ぐというよりも、装着した人から排出される微生物や感染源が外気中に広がるのを防ぐことが目的で作られたものです。
表面が防水加工されているのは、治療や手術時に患者の血液や体液が飛んできて、その中に含まれる病原体が侵入するのを防ぐことも目的としているからです。
手術時のサージカル用の規格
手術時のサージカル用の規格をしては、特殊不織布フィルターが採用され、細菌の濾過効率が95%以上で呼気抵抗が4.0未満、合成血液不浸透性が8.0mmHgで燃焼性がクラス1以下であることが要求されています。
一般的な医療用と家庭用のものは、特に規格がなく雑貨用品扱いとなっているので、メーカーによって表示や広告内容が異なります。
風邪や花粉症対策のために使われ、スーパーやドラッグストアでも良く市販されているものです。
ガーゼタイプや不織布で作られた使い捨てタイプがありますが、ほとんどは使い捨てタイプのものを使用しています。
顔の保温や保湿などを目的とされることもあります。
またフィルターが通気性や性能の良いものや耳に欠けるゴムが柔らかいもの、小さめのもの、眼鏡をかけても曇らないものや化粧品が付きにくいものなどバリエーションも豊富です。
マスクの性能を示す指標
性能を示す指標として、BFEとPFEというものがありますが、BFEは細菌を含む粒子の中で直径が4から5ミクロmの粒子を除去できた割合を示し、PFEは0.1ミクロmの試験用ポリスチレン製ラテックス球形粒子が除去された割合を示しています。
米国食品衣料品局はその割合が95%以上のものをサージカルにも求めていますが、市販されているものはその基準を満たしていないことが現状で、それを満たすものがN95ということになります。
WHOや厚生労働省は、医療機関においては飛沫感染にも効果を発揮するN95の着用を勧めています。
日本では、明治初期から主に防塵用として使用してきました。
真鍮の金網を芯にした布地にフィルターを付けたものでした。
1918年にスペイン風邪が大流行し注目されるようになり普及してきたという歴史があります。
1923年に内山武商店というところが商品登録品第一号として認定され、その後は金網をセルロイドに変えたりフィルターに別珍や皮などを使った製品が売り出されるなど改良がおこなわれました。
不織布性のプリーツタイプのものも1973年に誕生
1934年にインフルエンザの大流行でマスクの需要が高くなり出荷量も爆発的に増え、枠がない布だけのものもできました。
ガーゼを用いられるようになったのは、1950年代のことです。
不織布性のプリーツタイプのものも1973年に誕生し、1980年代に入ると花粉症が一般的になり、風邪やインフルエンザの感染防止や予防以外に、花粉症予防の目的で冬から春にかけて着用する人が増えました。
またインフルエンザやSARSなどの感染症が流行った時にも多くの人が着用していました。
2000年以降立体型のものも出てきたという経緯があります。
2020年の2月ごろから、新型コロナウイルスという肺炎を引き起こす病気が世界レベルで流行し、誰もが必要としたため日本全国いや世界中でマスクが店頭から無くなるという事態が発生しました。
長期にわたって店頭にないので、購入できなくて困っている人も増えましたが、それを悪用し、ネット販売で高額で販売し金儲けをする人も現れ、そのような状況に対して政府がネット販売業者に対して高額転売を禁止するなどの通達が出るという事態まで起こりました。
神澤光朗先生によるまとめ
そしてマスクメーカーは、不足を改善するべく製造に追われているのです。
2020年3月中旬になっても、新型コロナウィルスの感染者が増え続けているので、非常に需要が高くなっていますが生産が追い付かず、一か月以上店頭には並びません。
どの店に行っても「入荷未定」の状態なので、誰も新たに購入することができない状態が続いています。
そのため本来なら一回で使い捨てのはずのものを何回も使用してから捨てるようにしたり、手作りで作ることが推奨され、手作りキットなども販売されるようになりました。






