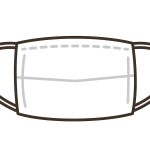最終更新日 2025年5月19日
産業医は一般企業においてその職場で働く労働者が健康で、さらに快適な作業環境のもとで仕事が行えるように指導をする医師のことを指しています。
一般的な内科医とは異なり労働衛生など専門的な知識が必要であり、労働者の健康を促進することを目指す活動を行うことが任務です。
目次
常時50人以上の労働者を使用している企業に限られている
この産業医はすべての企業に選任するのではなく、常時50人以上の労働者を使用している企業に限られており、中小企業や自営業者では選任していないことが多いです。
さらに人数なども細かく設定されており、事業者の義務として常時50人以上の労働者を使用する日から14日以内に選任をし、労働基準監督署に届ける義務があります。
産業医は労働者の健康診断の結果を把握することが仕事としてまずあげられます。
健康診断の結果を見て必要に応じて指導や助言を行います。
さらに近年多くなっているストレスにおいてもストレスチェック制度を用いて行い、ストレス不調に陥るのを予防していきます。
ストレス度が高い労働者においては医師の面接を行い適切に指導をし、悪化を未然に防いでいます。
2019年に行われた調査によるとメンタルの不調を訴えた労働者のうち、職場に人間関係が原因と答えた人が大変多いことがわかりました。
さらに人間関係が原因のうち約7割が上司との人間関係を原因としてあげています。
その後長時間労働や業務過多、パワハラと続いており、自分のスキル不足やプレッシャーなどは比較的少ない結果となっています。
企業との橋渡しをし中立的な立場にいる医師の存在が必要
職場の人間関係においては話しにくい部分があり、誰に話したらよいのか悩むことも多いです。
このような場合に企業との橋渡しをし、中立的な立場にいる医師の存在が必要となります。
この他精神的な不調によって休業している場合、復職に関して本当に適した時期なのかも診断しています。
主治医になることは難しいため、主治医との情報交換を行うことが大切であり、たとえ労働者が復職したいと考えていてもその結果からまだ適切でないと判断される場合は、もう少し休むよう促すのも仕事です。
また、職場においてメンタル面での不調を訴える人が多い場合は、人事労務管理や管理監督者に意見を述べ職場環境の改善も指導をしていきます。
月に1度は職場を巡回し、労働者の変化や職場の環境をチェックして改善すべき点は企業側に提案をするということも行います。
産業医は働く労働者と企業とを結びつける役割を担いますが、気軽に相談できる医師というわけではありません。
ストレスを感じている場合は面談を行い必要であれば会社に働きかけを行いますが、嘱託である場合は時間が限られているためすぐに相談をするのが難しい時があります。
治療や具体的な診断は基本的に行っていない
さらに一般的な医療機関とは異なり、治療や具体的な診断は基本的に行っていません。
必要に応じて医療機関を紹介するようになります。
大企業の場合は相談窓口が設置されていることが多いため相談窓口がまず一次対応を行い、その後相談となるので面談の予約を取る形となり、すぐに問題を解決できることは少ないです。
ですが仕事量や仕事内容が体の不調とつながっており業務の調整が必要は場合は、産業医が人事労務や上司に意見書を提出し残業や出張の停止、配置転換などを意見することができます。
1対1で話をするよりも第三者が入ることでスムーズに話し合いができることが多く、職場の環境を改善することにもつながります。
なお、上司などに報告することにより、不利になると考えられる場合は面談の内容などを共有するかどうかを相談者とともに考え、相談者の同意が得られない場合は無理やり話すことはありません。
あくまで同意がある場合に意見書は出されるので、相談者の不利益につながることがないように配慮されています。
産業医は職場においてのサポートが重点的
解雇に関与することもないので事実を的確に話をすることが大切であり、しっかりと医師と労働者が向き合うことで、より良い職場環境を造っていくことができます。
なお面談を行うのは雇入検診後や健康診断を行った後、長時間労働が多い場合、ストレスチェックにて高ストレスであり、医師の面談を受けたいと希望した場合、休職中や復職をしたい場合などが多いです。
健康診断の結果に問題がある場合は面談を行うことが一般的ですが、この時結果の悪さをたしなめることはなく、逆に見通しや症状に対しての治療方針などを相談することができるので、不安を取り除くことができます。
主治医が医療的な部分で治療やサポートを行うのに対し、産業医は職場においてのサポートが重点的であり、症状自体を回復することができるわけではありません。
医療の知識の他に会社の業務の知識が必要であり、医療機関と会社、そして労働者の橋渡しを行い支えていく目的があります。
まとめ
きちんとした企業であれば様々な意見を取り入れて、職場環境を整えていくことが多く、同僚や上司に相談できにくいこと、会社に知られたくないことなども話をすることができるので、余裕をもって相談日時を決めて話をすることが大切です。